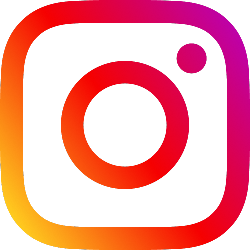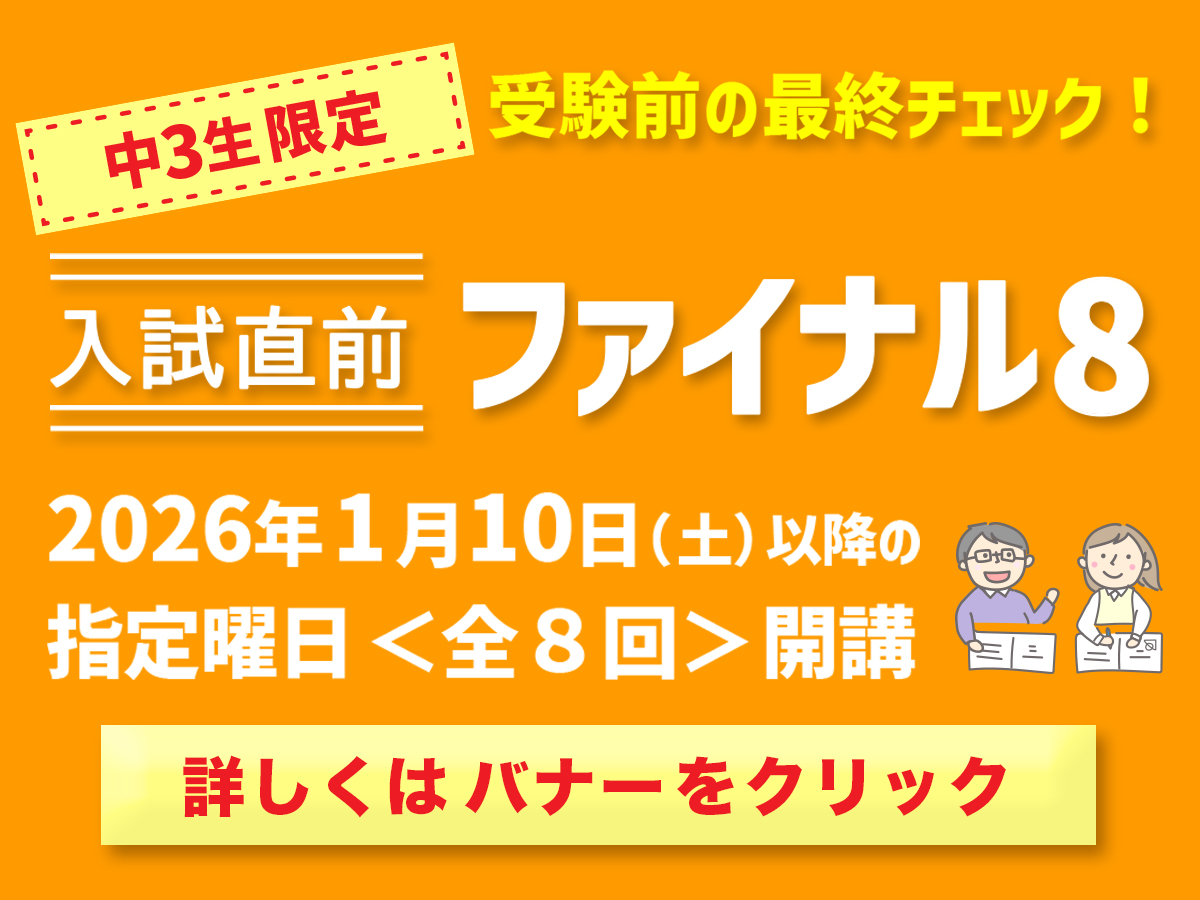講師ブログ
2025年3月18日
くりかえし原点、くりかえし未来。
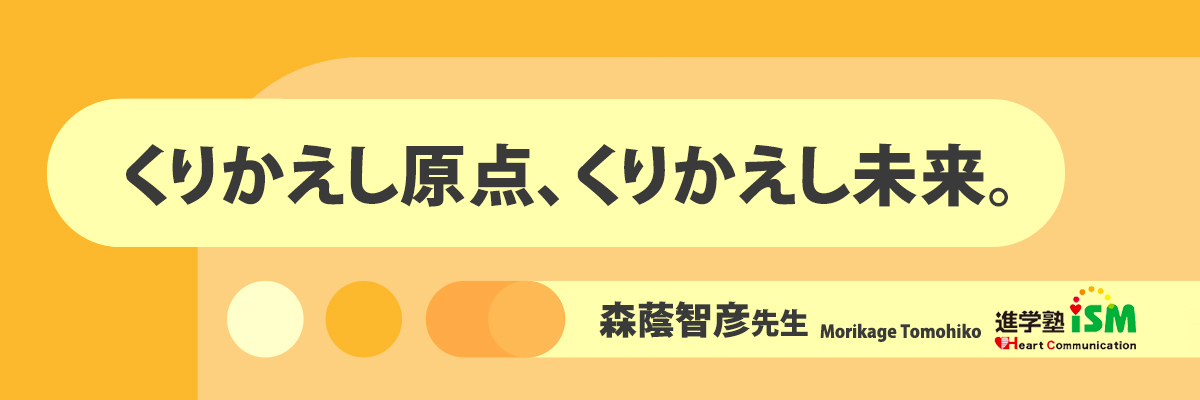
こんにちは、高校数学担当の森蔭です。
今回が今年度の講師ブログの最終回となりました。
今年度のISM生の国公立大学受験は、3月22日の愛知教育大学後期日程の合格発表をもって終了します。しかし、その後も私立大学の後期日程や、各大学の補欠合格者の発表がつづきます。ISM生の大学入試はまだまだ終わりを迎えてはいません。
今年の大学入試は新課程での初めての試験で、受験生にとってはこれまでの常識が通用しない、対策の困難なものでした。入念に準備をした共通テストは平均点が上昇し、その影響で難関大学のボーダーラインが大きく跳ね上がりました。これに伴って国公立大学入試前に行われた私立大学一般入試の合格率が減少し、難関国公立大学合格者でも私立大学が不合格となるような狭き門でした。
一方で、出願前の予想ではボーダーラインに大きな変動がないとされていた中位の国公立大学も、恐らくは難関大学からの出願変更の影響か合格の取りづらい状況となりました。ここまで見るかぎり今年の大学入試は、例年にない大荒れの結果となっています。それでもISMの生徒たちは、一丁の櫂のみを頼りにこの荒波を乗り越えようとしています。ここまでの道のりは決して順風満帆なものではなく、荒れ狂う波に抗いながら行きつ戻りつを繰り返す日々でした。そんな中、私はひたすら彼らの行く手を照らす明かりにしかなりえませんでした。
長らく高校生の学び舎であったISM 2号館が、新年度から現在の1号館と3号館をリニューアルし移転することになりました。先日、授業が終わり誰もいなくなった校舎で一人きりになる時間がありました。目を閉じて静かにしていると、この10余年にあった出来事や生徒たちの顔・声が走馬灯のように頭の中を駆け巡りました。これまでの時間で、私はどのように振舞えただろうか。生徒たちの未来のために少しは役に立てたのであろうか。もっとできることがあったのではなかろうか。不安と後悔の念に苛まれていたとき、誰かが校舎の扉をノックする音に気が付きました。扉の方に行って見ると4年前にISMを卒業し、4月から新社会人になる2人の卒業生が立っていました。聞けば、地元に帰郷したため、わざわざ就職の報告をしに来てくれたとのことでした。彼らのあまりにも変わらぬ姿に、私は一瞬タイムスリップをしたかのような不思議な感覚を覚えました。10分ほど話した後、彼らは丁寧に夜分の訪問を詫びて立ち去っていきました。
学生時代に読んだ、九鬼周造の処女作『時間論』を思い出しました。九鬼はドイツでハイデガーに、フランスでベルクソンに直接教えを受けた稀有な日本人で、生涯「時間」にこだわりつづけました。西洋では、時間は分割された点であり、それらが無数に並んで直線をなすと考えられています。その線は無限の過去から無限の未来へと延び、過去から未来へと一方向にのみ進みます。決して逆には進みません。しかもこの原則は宇宙のどこでも成り立っていると考えるのです。九鬼は『時間論』の中で、西洋の直線的な時間観に対して、東洋的で円環的な時間観を提示します。朝・昼・夜、春・夏・秋・冬が何度も繰り返されるように、時間は必ずしも直線的であるとは限らない。そこには「永遠の未来」ではなく「永遠の今」がある、というのです。私は、2人の卒業生と過ごしたほんのわずかの時間により、学生時代にはわからなかった九鬼の提唱する「回帰的形而上学的時間論」が少し理解できたような気がしました。
生徒たちがISMで過ごした時間は、ある意味では大学合格という未来に向かって延びる直線的なものだったかもしれません。一方でそれを毎日の生活の視点からみれば、朝起きて学校に行き、その後ISMに来て勉強をして帰宅し就寝するということを繰り返す、円環的なものだったかもしれません。だからこそ、その直線や円は平面的なものではなく螺旋状に「周りながら延びていく」立体的な構造をもつものに違いありません。そして何より、この時間という構造物は一方のみに進むものではなく、時として逆の方向にも進みうるのです。ただしそのためには、立ち返るべき「永遠の今」が必要なのです。
今、無印良品の創始者のひとりである小池一子さんの「くりかえし原点、くりかえし未来。」という言葉が私の頭の中を巡っています。ISMがここに関わるすべての生徒たちにとって「原点」であり「未来」であることができるように、そしてここが「永遠の今」でありつづけられるように、私はこれからもISMを守り育んでいきたいと思います。